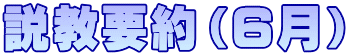
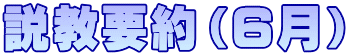
2018年6月24日(日) 説教題:「ゆるされて、ゆるして」 聖書;マルコによる福音書6章14~29節
ヘロデ王は、いわゆる王様ではありませんでした。すでに、ローマ帝国の支配が確立した時代に彼は傀儡政権として建てられたのであり、父ヘロデがそうであったように王と名乗りたいという権力欲がそうさせたのでしょう。ヘロデのプライドの高さは色々と問題があったのでしょうが、最も大きな失敗は、彼の誕生日に信頼する洗礼者ヨハネの首を切らなければならないという出来事でした。
洗礼者ヨハネには権力を恐れない人でしたから、ヘロデの結婚相手にも法律的な問題があることを指摘していました。その恨みを買ったため、ヘロデの妃によって罠を仕掛けられ、ヘロデ自身が手を汚すことになりました。
人は、自分の発した言葉を守らなければなりません。もし、そうではなくても、間違ったことを認めて訂正することは難しいのです。ヘロデも誕生会の席で大言壮語したことから、ヨハネを失うことになりました。
渡辺和子さんの本で読んだ記憶がありますが、「人は言葉を頭で考えている時は自由に作ることができるが、一度でも発してしまえば、その言葉に従わなければならない。」というものです。
この場面ではヨハネが無残な死をとげたことだけが印象的ですが、大切なのはヨハネからイエスへと時代が変わったことです。み言葉を預言者から聞いていた時代から、直接み言葉を聞いて行う時代へと変わったのです。
さて、ヨハネはどう思っていたのでしょうか。人生半ばの最期を思ってヘロデを憎んでいたように感じます。しかし、彼は牢に入ってもヘロデと語り合っていました。いつでも受け入れ、ゆるしてしたのです。
結局、ヘロデはゆるされていたことを知りませんでした。気付いていたけれど、ゆるすことは出来ませんでした。何よりも、ヨハネの出来事で自分をゆるせなくなったでしょう。だからこそ、キリストの十字架があるのです
2018年6月17日(日) 説教題:「神の子として生きる」 聖書;マルコによる福音書6章1~13節
歌「ふるさと」を聞くと、見たこともない情景でありながら、何となく、懐かしさを感じてしまいます。作曲の岡野貞一は鳥取県出身で、ここ鳥取では有名人ですが、作詞の高野辰之についてはよく知りませんでした。
少し高野氏について調べてみると、長野県出身の代々農家の家の息子だったようです。文学に優れ、歌を作る能力を磨くために東京へと学びに行ってからは、故郷の長野へ帰京することは少なかったようです。
「ふるさと」の3節には両親について歌っていますが、残された手紙には母を思う言葉が並べられており、帰京することは少ない分、母への思いは募ったことでしょう。
その反面、父について書いている文書はあまりないようです。高野氏の父は農家でありながらも非常に勉強に熱心で、しかも優秀だったようです。想像するに、農家でありながら勉学することを批判する人たちも多くいたのでしょう。そのような父の姿を見て高野氏も学ぶことへの意欲が与えられ、こうして、多くの歌を残す文学者となりました。
聖書でも同じように、イエス様が故郷に帰って後、ヨセフの子として見られたことが書かれています。それは、人間が誰から生まれ、どこで生まれたかで生き方が決まるという考えがあるからです。
しかし、イエス様は「神の子」として生きる姿を見せています。どのような境遇であれ、誰の子であれ、人は神に愛されて、自由に生きることができることを見せています。
私たちは気付かない内に自分で制限をかけ、自分で縛ることがあります。人の言葉は人を縛りますが、神の言葉は人を解放するのです。
2018年6月10(日) 説教題:「神さまがして下さったこと」 聖書;マルコによる福音書5章1~20節
聖書が書かれた時代は今よりも情報や知識が少なく、迷信や理解不足が多くありました。ここでは、狂ったように振る舞うゲラサの人を悪霊がとりついたと表現しています。
このゲラサの人は墓に住んでいました。悲しみから別れることが出来なかったのでしょうか。そして、信じられない力で暴れたり、叫んだりして周りの人々は恐れていたようです。
一見すると、気が振れた人のように見えるゲラサの人ですが、悲しみの中で狂ってしまわないとは言い切れないでしょう。何よりも、この苦しんでいる姿は、私たちの内面にあるもう一人の「わたし」の姿でもあるように思います。
ゲラサの人はイエス様に名前を聞かれましたが答えませんでした。その代わりに「レギオン」と言う言葉を出しています。「レギオン」とは当時の軍隊の単位で6000人の一個大隊を意味します。
この人が「レギオン」と答えたには意味があります。まず、名前を明かさない匿名性を求める姿からして、多くの人間の集団で身を潜める個人のように見えます。そして、その集団の中で深刻な孤独に陥り、悲しみを理解し合う友もいないのではないでしょうか。
イエス様と出会い、自分の気持ちをぶつけることができ、人間へと帰っていくゲラサの人。最後には、キリストに従って生きるとは、神様がして下さったことを思い出し、それを伝えることだと言われています。
私たちは多くの失敗と誤りを背負って生きています。と同時に、そこに神様がして下さったとしか思えないような不思議なことも起こります。悲しみの中に喜びがあり、喪失の中に発見があるのです。信仰はそれを見つける灯なのです。
2018年6月3日(日) 説教題:「伝道する教会」 聖書;マルコによる福音書1章29~39節
もう、15年以上前のことになりますが、わが教団で「それいけ、伝道!」と言う言葉が流行りました。当時の印象としては、何だが浮かれた気分になる言葉でしっくりきませんでした。地に足を付ける教会の活動とは何かと考えていました。
超高齢者社会を迎える日本とその中にいる教会は、次世代を産み出すことが難しい難産の時代に入っています。そこで教会に人を集めようとして、魚の網をあちらこちらに投げうつように、とりあえず「伝道」と言わなくてならない雰囲気にあるように感じています。
聖書では「伝道」と言う言葉はなく、「伝道者」と言う言葉で用いられていたようです。ヘブライ語で「集める」と言う意味を含むコーへレスが使われています。それは、集会の場で語る者と言う意味になり、「伝道者」と訳されました。
今の「伝道」と言うイメージを強く作ったのは英国教会で1918年に作られた伝道に関する文書だったと思います。その中で伝道の結果は教会に帰ってくるという意味の言葉が書かれています。
日本だけでなく全世界へと宣教者を派遣したこの時代に、カトリックもプロテスタントも正教も関係なく、キリスト教の伝道とは教会に人を増やすことだったと読みとることが出来ると思います。
時代は流れ、その伝道観と結びついたのは植民地支配であり、精神的支配にキリスト教が利用されることとなった反省から、1952年に「他者のための教会」として歩みだすことになりました。
その意味で宣教とは教会の思いを他者に向けるのではなく、教会に招く人の思いに教会が寄り添うためにあるということなのでしょう。支配ではなく、解放を伝えることなのです。